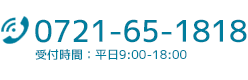10月6日は十五夜でした。陰暦の8月15日にあたるこの日は「中秋の名月」とも呼ばれ、一年で最も美しい月が見られる日とされています。
中国で発祥し日本に伝わった「お月見」の風習は、奈良時代から平安時代の貴族を中心に広まりました。当初、貴族たちは月を愛でながら音楽や和歌を楽しみましたが、時代が下るにつれて武士や農家、庶民にも伝わり、秋の収穫を祝い感謝する行事としての側面も持つようになりました。
「ふれあいの丘」でもこの日の昼食は、十五夜にちなんで秋の豊かな実りを感じられる献立をご用意しました。

この日のメインは「吹き寄せ寿司」です。関東風のちらし寿司の一種で、茹でエビ、鰻、錦糸卵、銀杏などを彩りよく盛り付けました。「吹き寄せ」とは「さまざまなものを寄せ集める」という意味の言葉。風で落ち葉や木の実が“吹き寄せ”られたような、実りの秋から冬枯れを連想させる情緒があります。
冬枯れにはまだ遠く、残暑の厳しい日が続いていますが、徐々に日が短くなり季節の移り変わりを感じています。
週末の地域の地車祭(だんじりまつり)を控え、夕方の高野街道もすっかり日が落ち、提灯の明かりが映えるようになりました。