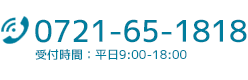施設内研修として、今回は河内長野市中部地域包括支援センターの職員の方を講師にお招きし「高齢者虐待」をテーマに研修を行いました。地域のお困りごとに日々向き合われている専門職の視点から、「どこからが虐待にあたるのか」という線引きについて深く学ぶことができました。
高齢者虐待防止法と虐待の種類
2006年4月に施行された「高齢者虐待防止法」は、高齢者の権利と利益を守ることを目的としています。この法律では、高齢者虐待を「養護者による虐待」と「養介護施設従事者等による虐待」の2つに大きく分類しています。どちらのケースも、介護負担やストレスの蓄積、あるいは認識不足や配慮の欠如から発生することが少なくありません。

今回の研修では、高齢者虐待防止法で定められている以下の5つの虐待について詳細な説明がありました。
• 身体的虐待
• ネグレクト
• 心理的虐待
• 性的虐待
• 経済的虐待
説明後は、具体的な事例をもとにグループで活発な意見交換を行い、「これは虐待にあたるのか」「どのような種類の虐待か」を議論しました。また、「虐待の芽」チェックシートを用いて、虐待に繋がりうる心理や状況を再認識しました。
虐待は「他人事」ではない
高齢者虐待は、介護者の負担や適切な介護方法の知識不足など様々な要因で発生します。決して他人事ではなく、どの家庭や施設でも起こりうる身近な問題として理解することが重要です。また、介護者が孤立しないよう、家族内での協力や同じ悩みを持つ人との交流も非常に大切です。
当施設「ふれあいの丘」は建物内に中部地域包括支援センターを併設しており、養護老人ホームのご利用者様には当事者経験をお持ちの方もいらっしゃいます。このような施設形態は全国的にも珍しく、私たちは決して虐待を発生させてはならないと強く意識しています。今回の研修を通じて職員一人ひとりが日々の振る舞いが虐待にあたらないかを常に意識し、職員同士で気をつけあうことの重要性を改めて強く感じました。
もし、高齢者虐待に関するお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、お住まいの地域の地域包括支援センター、または市区町村の地域福祉関連部署にご相談ください。専門機関がきっとあなたの力になってくれます。